石材・灯籠の種類

歴史と風情を灯す、植竹石材店の灯籠
植竹石材店では、古風で味わい深い灯籠のみを取り扱っております。現代では採掘が難しい希少な石材や、歴史を感じる古材を使用した灯籠が私たちの自慢です。
時を超えてなお輝きを放つ、風情ある灯籠との出会いを、植竹石材店がお手伝いいたします。

取扱い石種
真壁石 MAKABE STONE
日本を代表する花崗岩の銘石
茨城県桜川市真壁町で産出される真壁石(まかべいし)は、堅牢で美しい花崗岩として、日本の石材業界において確固たる地位を築いています。常陸三山(筑波山・加波山・足尾山)の懐に眠るこの石は、その優れた耐久性と風格ある質感で、古くから墓石や建築材、美術品などに幅広く活用されてきました。
そして真壁石は、建てた時が最も美しいだけでなく、時間の経過とともに重厚感が増し、落ち着いた風合いが生まれるのも大きな魅力です。長い年月を経ても、その価値が損なわれることがないため、古くから人々に選ばれ続けています。

真壁石の特徴
真壁石は、石英・長石・黒雲母から成る白系の花崗岩で、以下のような特徴を持っています。
高い耐久性

経年変化が少なく、黄ばみやサビなどの変色が起こりにくいです。
優れた美観

時間の経過とともに重厚感が増し、落ち着いた風合いが生まれます。
加工のしやすさ

堅牢でありながら適度な粘りがあり、加工しやすい特性を持っています。

真壁石の種類
真壁石は、石目の大きさによって大きく二つに分けられます。
- 真壁小目石
- 細かい石目と青みがかったグレーの色合いが特徴。
- 真壁中目石
- やや大きめの石目で、白みがかったグレーの色合い。
関東の石材業界では、それぞれ「小目」「中目」と略して呼ばれることが多く、一般的な墓石材や建築材として広く流通しています。

真壁石が支持される理由
真壁石がこれほどまでに広く用いられる理由の一つに、品質の安定性があります。採掘業者の間でも「時間が経つほどにその価値が増す石」として評価されており、長期にわたる使用に適していることが証明されています。
また、日本国内における石材三大産地の一つとして知られる真壁地域は、優れた石材加工技術を誇ります。その中心的な役割を担うのが、私たち植竹石材店をはじめとする地元の石材業者です。熟練の職人たちが伝統の技を受け継ぎながら、時代に合わせた新たな加工技術も取り入れ、常に高品質な製品を生み出し続けています。
筑波石 TSUKUBA STONE
悠久の時を刻む、趣深き黒石
日本の庭園文化において、石は単なる装飾ではなく、時の流れや自然の調和を表現する重要な要素です。その中でも筑波石は、茨城県つくば市の筑波山で採れる特別な黒御影石であり、時間とともに変化する独自の風合いを持つことから、多くの造園家や石材愛好家に選ばれてきました。
筑波山の豊かな自然が育んだこの石は、歴史ある庭園から現代のモダンな空間に至るまで、幅広く活用されています。
筑波石の特徴
筑波石は、茨城県つくば市の象徴ともいえる筑波山で採れる黒御影石の一種で、現在では大変貴重な存在です。
地質学的には「斑レイ岩」に分類され、表面には自然石ならではのざらつきがあり、全体的に丸みを帯びた形状をしています。採掘された直後は乳白色を帯びていますが、時間の経過とともに黒褐色へと変化し、風合いが深まるのが特徴です。この経年変化が、筑波石ならではの魅力となっています。

筑波石の種類と用途
筑波石は、庭園の景石として一石で据えるだけでなく、石組みや石積みとしても使われます。その黒灰色の落ち着いた色味は、他の石材と組み合わせることで一層洗練された空間を生み出します。
特に、筑波石の黒色は、同じ茨城県の桜川市で採れる白砂利(御影石の細粒)と相性が良く、互いを引き立て合うことで調和の取れた景観を演出します。

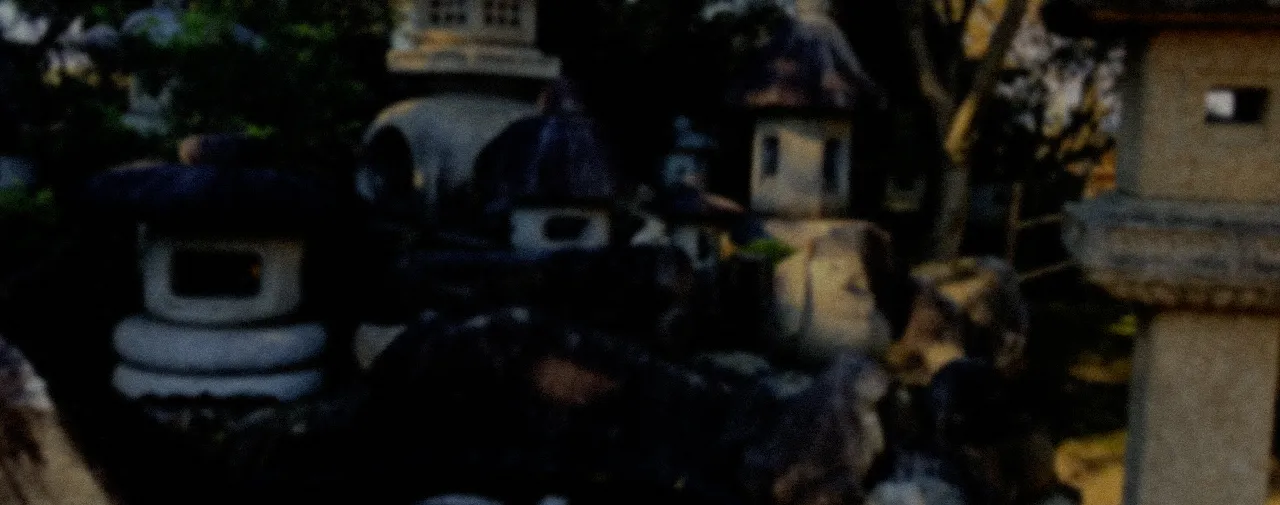
筑波石が支持される理由
筑波山は、男体山と女体山という二つの峰が特徴的な山であり、関東平野からその雄大な姿を望むことができます。その山麓や中腹で産出される筑波石は、まさにこの地の風土を映す存在であり、地域の自然素材を活かした庭づくりに最適な石材として、多くの造園家や愛好家に選ばれています。
さらに、時間とともに変化し、風格を増していく「生きた石」である筑波石は、移ろいゆく美しさを楽しむことができる、唯一無二の石材として支持されています。
取扱い灯籠

台付形石灯籠
美しく堅牢で、変色しにくく水分の吸収も少ない高品質な石材を使用。建築物や墓石に広く用いられ、明治32年の迎賓館造営をはじめ、皇居の縁石や三越本店など著名な建築にも使用されている。

生込形石灯篭
基礎部分がなく、柱を直接地面に埋め込む灯篭。高さの調整が可能で、露地の明かりや蹲踞(つくばい)周りに適している。比較的小型で軽量なため、個人での設置も容易。

雪見・蘭渓・勧修寺石灯籠
傘を広げた形が雪の積もった姿に似ていることから名付けられた低めの灯篭。池や墓地周辺に設置され、足元を照らす役割を持つ。水辺に置くことで水面を美しく照らす効果もある。

手水鉢・水盤
手や口を清めるための石製の鉢。手水を受けるための「海」と組み合わせて設置される。「つくばい」という名称は、手水を使う際にしゃがむ姿勢(蹲う)に由来する。

置灯篭
庭石や地面に直接置く小型の灯篭。2~5つの部品で構成され、庭の景観を引き立てる。暗い庭でも足元を照らし、織部灯篭など多彩なデザインが楽しめる。

山灯篭
自然石を組み合わせた石灯籠で「化け灯籠」とも呼ばれる。奈良時代から仏堂に献灯され、江戸時代以降は神社の参道や入口にも多く設置された。適切な形やサイズの石を選び、一体として調和させる技術が求められる。

彫刻物
灯篭の彫刻物は、その細やかな技巧と独特の風合いが特徴です。石の質感を活かしながらも、繊細な彫り込みによって生まれる陰影が、幻想的な光と影のコントラストを生み出します。
植竹石材店の灯篭は、先代実様の弟様が研ぎ澄まされた感性で創り上げた、唯一無二の作品です。素材と真摯に向き合い、妥協なき手仕事で刻まれた彫刻は、時を超えて今もなお、その存在感を放ち続けています。



